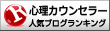こんにちは!心理カウンセラーの松田ちかこです。
子どもの成長の目安って、実際のところよくわからないですよね。
母子手帳の発達曲線のラインより上かな下かな・・・
何か月で、何歳で、どんなことができればいいの?
身体の成長や運動面の成長、勉強面での成長などを中心に一喜一憂することが多いと思います。
しかし、一番見過ごされがちなのは、精神面での成長です。
今回は『心の発達』について、お話ししたいと思います。
はじめに
多くの人は、身体の成長や運動面、勉強面での成長などに一喜一憂することが多いと思います。
これらの側面は、一人ひとりペースに違いがあり、一つひとつ進んでいれば神経質に気にし過ぎる必要はないと思います。もちろん、大幅な違いがある場合は医療機関などに相談してくださいね。
この”目に見える”部分は注目しやすいのですが、問題は”目に見えない”部分、つまり『心』に注目しにくいことです。
『心』は何となく、最初から変わらない”素質”のように捉えられがちですが、生まれた時から死を迎えるまで、ずっと成長し続けているものなんです。
「誰と」「どんな環境で」「どう関わったか」がその成長に大きな影響を与えます。
生理的欲求を満たしていれば、身体は成長し、見た目は年相応になります。
しかし、その『心』は年相応かどうかは別問題です。
人間関係の軋轢は、見た目から想定している心の年齢と実際の心の年齢に差があり、それをお互いに理解できないことから始まっている、と言っても過言ではないと思います。
実際、虐待を受け、大人との安定的な心のやり取りができなかった子どもたちの多くは、心がすごく幼い場合が多いです。
それだけ、『人間』として心を成長させるために、大人がどう関わり、どう心を通わせるかが重要になってくるのです。
そもそも『発達』とは?
『発達』とは、人間の身体や心の構造・働きに生じる連続的な変化のことです。
「成熟」という遺伝的に親から受け継がれたものによって生じる、環境の良し悪しとはほとんど関係がなく変化するもの。そして、「学習」という経験の結果によって生じる環境がどうあるかによって変わる比較的永続的に変化するもの。この2つの側面があり、これらの相互作用によって発達は生じると考えられています。
持って生まれた「素質」による成熟 × 身のまわりにある「環境」による学習 = 『発達』
ということです。
また、発達の各時期には『発達課題』という、達成を期待される課題があります。それを達成することで発達が促進されます。
心の発達課題については、次に挙げる発達心理学者が唱えた説を見ていきましょう。
発達段階
エリクソンの発達段階説
アメリカの心理学者エリクソンは、人間の一生を8つのステージに分け、各ステージに身に付けなければならない特有の課題を見出しました。
課題を達成することで、新たな能力が身についたり、精神的な成長を遂げたりしますが、課題を達成せず未解決のまま残してしまうと、「心理的危機」を招くとしています。
| ステージ | 発達段階 | 年齢 | 発達課題 | 心理的危機 | 活力(徳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳児期 | 0~1.5歳 | 基本的信頼感 | 不信 | 希望 |
| 2 | 幼児前期 | 1.5~3歳 | 自律性 | 恥、疑惑 | 意志 |
| 3 | 幼児後期 | 3~6歳 | 自主性 | 罪悪感 | 目的 |
| 4 | 学童期 | 6~12歳 | 勤勉性 | 劣等感 | 有能感 |
| 5 | 青年期 | 12~22歳 | 自我同一性 | 同一性拡散 | 忠誠 |
| 6 | 成人初期 | 22~40歳 | 親密性 | 孤立 | 愛 |
| 7 | 成人期 | 40~65歳 | 生殖性 | 停滞 | 世話 |
| 8 | 成熟期 | 65歳以上 | 自我の統合 | 絶望 | 英知 |
表1 エリクソンの発達段階説
第1ステージの発達課題は、基本的信頼感の獲得です。
養育者から安定した養育を受けた経験を通して、乳児は世界に対する最初の信頼感を身に付けます。これがうまくいかないと不信感が強くなり、愛着の形成に影響を与える時期です。
<重要な関係>母親的人物
第2ステージの発達課題は、自律性の獲得です。
排泄や自立歩行の訓練の体験を通して自律性を獲得します。失敗をすれば恥ずかしい気持ちを抱き、自分の力に疑惑を持つこともあります。養育者には、子どもの恥や疑惑の気持ちを和らげて、自律性が獲得できるように工夫して関わることが求められます。
<重要な関係>親的人物
第3ステージの発達課題は自主性の獲得です。
このステージでは遊びを中心にして、自分で何かを解決したりいろいろな遊びに挑戦しようとするような自主性を獲得します。大人と比較することを覚え、男女の違いにも気がつくようになります。
<重要な関係>基本家族
第4ステージの発達課題は勤勉性の獲得です。
学校教育を受けるようになり、それを通して勤勉性を身に付けます。しかし、失敗体験も多くなり、劣等感を形成しやすいのもこの頃です。
<重要な関係>「近隣」、学校
第5ステージの発達課題は自我同一性の獲得です。
「自分とは何か」「これからどう生きていくのか」「どんな職業に就いたらよいのか」「男として、女としてどう行動したらよいか」といった問いを通して、自分自身を形作っていく時期です。「これこそが本当の自分だ」といった実感のことを自我同一性と呼び、青年期は、この自我同一性を獲得するための社会的な義務や責任を猶予されている準備期間(モラトリアム)であるといえます。この時期は、試行錯誤を通して、積極的に自己形成していける貴重な時期です。
同一性拡散の状態にあると、非行に繋がってしまう可能性があります。
<重要な関係>仲間集団と外集団
第6ステージの発達課題は、親密性の獲得です。
配偶者や仕事仲間との親密な関係を築くことが課題です。
<重要な関係>友情・性愛・競争・協力の関係におけるパートナー
第7ステージの発達課題は、生殖性の獲得です。
家庭では子どもを養育すること、社会では後継者を育てることを通して、次世代を育成するという生殖性を獲得することが課題です。
<重要な関係>労働と家庭
第8ステージの発達課題は、自我の統合の獲得です。
人の生涯発達のゴールは自我の統合ということです。そのようになって初めて、人間は死を苦痛を伴わないものとして考えることができます。この統合がうまくいかないと、自分の一生をあるがままに受け入れられず、死の恐怖にとらわれるようになります。
<重要な関係>「人類」、「種族」
ピアジェの認知発達段階説
認知機能の発達について、スイスの心理学者ピアジェは論理的思考を中心に認知発達段階説を提唱しました。
子どもの認知機能の発達を、子ども自らが周囲に働きかけ、環境との相互作用を通して、順を追って展開していくことを明らかにし、子どもが周囲を認識する「シェマ(スキーマ構造)」の変化を4つの発達段階として区分しています。
| ステージ | 発達段階 | 年齢 | 特徴 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感覚運動期 | 0~2歳 | 言葉の使用によらず、自分の目の前にあるものを見たり触れたりすることによって、自分をとりまく世界と認知の適応をはかる時期 (感覚と運動が直接結び付いている) |
||
| 2 | 前操作期 | 2~7歳 | 実物によらなくても、言葉などを用いた知的活動が可能となるが、具体物の見えに影響され、論理的思考は十分に行われない時期 (他者の視点に立って理解することができず、自己中心性の特徴を持つ) |
||
| 3 | 具体的操作期 | 7~11歳 | 具体物や具体的状況においてのみ論理的思考が可能である時期 (数や量の保存概念が成立し、可逆的操作も行える) |
||
| 4 | 形式的操作期 | 11歳~ | 帰納、演繹など、言語や記号を用いた抽象的な論理的思考が可能となる時期 (形式的、抽象的操作ができる) |
||
表2 ピアジェの認知発達段階説
感覚運動期には(物を触る、声を上げるなど)動作により周囲の世界と関わっていきます。そして、それが次第に内在化して言葉やイメージによる”思考”が芽生え、内的思考(頭の中で考える)を行っていくという段階が前操作期です。その後、論理的な思考を徐々に獲得し、具体的な場面を対象として論理的思考ができるようになるのが具体的操作期で、概念や記号を使ってさらにより抽象的で論理的な思考ができるようになるのが形式的操作期です。
各段階において「シェマ」を周囲の世界に当てはめて適応しようとし(同化)、うまくいかないときは「シェマ」を変化させて適応しようとする(調節)ことで、安定した認識を得、この過程を繰り返すことで、思考(認知機能)が発達します。
発達課題をどう達成していけばいいのか
エリクソン、ピアジェどちらの説でも共通するのは、前の発達段階での経験・獲得した力が次の発達段階に統合されて発達が進んでいくという点です。
発達は個体として元々持っている「素質」と周囲からどのような刺激を受けるかという「環境」の相互作用により生じます。
具体的には、「素質」は遺伝的要素や気質などのことで、「環境」は人との関わりや生活環境などのことです。
発達課題を達成するためには、この「素質」を見極め、「環境」としてどんな関わりをし、何が身のまわりにある状態にするのかを発達課題を踏まえて考えることが重要なのです。
つまづきに気付いた場合どうすればいいのか
例えば、エリクソンの発達段階説の第1ステージの発達課題である基本的信頼感の獲得ができなかった場合、人を信頼することができず、愛着障害に繋がっていきます。
発達課題を達成できないことで、周囲の世界に対して認知のゆがみを抱えたまま生きていくこととなり、それが非行や犯罪に繋がったり、精神疾患に繋がったりしてしまうことがあるのです。
発達課題のつまづきに気付いた場合、その段階に戻り課題を達成することが必要となります。病院や療育施設などに相談しサポートを受けながら、子どもの素質や今の状態をよく知り、関わり方や生活環境を見直しましょう。
保護者サポートとして、カウンセリングやペアレントトレーニングを受けてみることも一つの案です。
発達は積み木を積み重ねるように進む
心の発達は、一つひとつ積み木を積み重ねるように進みます。今、手に持っている積み木を重ねないと、次の積み木は積めません。乱雑に積むといつか崩れます。
エリクソンやピアジェの発達段階説を参考にしながら、子どもの素質や特性を考慮して、安定した心の発達をサポートすることが、大人の役割なのだと思います。
崩れないように積み木を積むには丁寧に時間をかける必要があります。「面倒だ」と思うかもしれません。でも、そこから逃げてしまうとどうなりますか?
丁寧に積み上げ素敵なお城が出来たら、きっと関わったみんなが笑顔になっていますよね。
最後に
一人の人間として自立して生きていく力。子どもから大人になるまでの間にこの力を身につけてあげなければなりません。勉強や運動も生きていく上で必要なことです。しかしそれは、安定した心がベースにあることで、伸ばしていけるものだと思います。
着実に心が発達できているのか確認をすること、積み重ねられているところまで戻る勇気も大切です。発達のペースは人それぞれ。素質も人それぞれ。焦ることなく、積み木が崩れないよう、一つひとつ着実に積み重ねていくことが出来ればいいのです。
このブログを読んでくださった方には是非、関わる子どもたちの「心の発達」に注目して、その子に合わせた関わりで発達の促進をサポートしてもらえると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございます
▽いいね♡
【匿名電話カウンセリング ボイスマルシェで活動しています🌸】
・誰かに聴いてもらいたい
・どうすればいいかわからなくて苦しい
・不安で眠れない
・子育ての悩み
・身近な人の発達障害の悩み
🍀こんな時はお気軽にご相談ください🍀
▽ボイスマルシェでのご予約はこちらから
https://www.voicemarche.jp/advisers/1006
※女性専用となります。
▽ブログの順位を見る
▽『心理カウンセラー 松田ちかこ』ってどんな人?
▽最新情報・豆知識をチェック
▽また読みたいな
▽こちらも合わせてお読みいただけると嬉しいです
<参照>