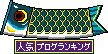こんにちは!心理カウンセラーの松田ちかこです。
5月5日は五節句のひとつ「端午(たんご)の節句」です。別名を「菖蒲(しょうぶ)の節句」とも言います。
現代では、こどもの日として親しまれていますよね。
「端午」とは、午の月(五月)の端(最初)の午の日という意味があります。もともとは最初の午の日に節句を祝っていたのですが、午と五が同じ音ということから5月5日となったそうです。
季節の代わり目の儀式として、菖蒲などの薬草で厄除けをするという風習が中国から伝わりました。菖蒲の強い香りが厄を祓うとされ、菖蒲湯で心と身体を清めるようになったと言われています。

また、鎌倉時代以降になると「菖蒲」が「尚武(武を尊ぶこと)」と同じ音であることや菖蒲の葉の形が剣を連想させることなどから、武家の間で盛んに祝われるようになりました。武家の跡取りとなる男の子。その成長を祝い、健康を祈るようになったことから、現代の男の子の健やかな成長を祈る日につながったということです。
鎧や兜を飾るのも、この武家社会から生まれました。
自分の身を守る大切な道具である鎧兜は、現在では事故や病気などから大切な子どもを守る意味も込められるようになったんですね。
鯉のぼりは江戸時代になってから町人の間で生まれ、関東の風習として全国に広まりました。
鯉はとても生命力が強いことや、「登竜門」という言葉の由来となった、竜門という急流を登りきった鯉は竜になるという言い伝えに因んで、子どもが厳しい環境にも耐え、立派な人になるようにとの願いを込められて飾られるようになりました。
飾り物の他に、かしわ餅やちまきを食べる風習もありますが、かしわ餅は日本独自のものです。"柏は新芽が出るまで古い葉が落ちない"ことから"家系が絶えない"縁起物として広まりました。
楚国の詩人で王の側近であった屈原(くつげん)という人物が、陰謀により国を追われ、河に身を投げてしまいました。命日の5月5日に、屈原の死を嘆いた人々が米を詰めた竹筒を捧げましたが、河に住む竜に食べられてしまうため、竜が嫌う葉で米を包み、五色の糸で縛ったものを河に流すようになったことから、ちまきが生まれたと言われています。
日本には奈良時代に伝わり、端午の節句にちまきが用いられるようになりました。「ちまき」とは茅(ちがや)の葉が使われたことからそう呼ばれるようになったと言われています。
端午の節句の色々な風習には、こうした由来があるんですね。
いつの時代も人は人を思い、子どもの明るい未来を願う。
節句の風習を知るだけでも、脈々と受け継がれる先人からの温かな思いが感じられますね。
少しでも多くの子どもたちが心躍る一日を過ごし、満たされた気持ちで眠りにつけますように。
最後までお読みいただきありがとうございます
▽いいね♡
▽現在のランキング順位を見る
【匿名電話カウンセリング ボイスマルシェで活動しています🌸】
・誰かに聴いてもらいたい
・どうすればいいかわからなくて苦しい
・不安で眠れない
・子育ての悩み
・身近な人の発達障害の悩み
🍀こんな時はお気軽にご相談ください🍀
▽ボイスマルシェでのご予約はこちらから
https://www.voicemarche.jp/advisers/1006
※女性専用となります。
【ココナラでメールカウンセリングをしています🌸】
・発達が気になるお子さんの子育てについて
・お子さんの困った行動への悩み
・保育園などの福祉施設の職員さんが抱える支援の悩み
🍀こんなお悩みをご相談ください🍀
▽『心理カウンセラー 松田ちかこ』ってどんな人?
▽最新情報・豆知識をチェック
▽また読みたいな
▽著書
▽こちらも合わせてお読みいただけると嬉しいです