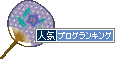こんにちは!心理カウンセラーの松田ちかこです。
今の世の中は「多様性を受け入れていこう」という風潮がありますよね。
子育てにおいても、子どもの多様性を尊重した関わりが求められるようになっています。
しかし多くの人が「多様性を受け入れるって言ってもなんとなくしか分からない」という気持ちを抱えているのではないでしょうか。
多様性を受け入れるのにまず必要なのは、「自分と他者は違うこと」を“知ること“。
自分と他者は違う存在であること、その違いはそれぞれ素晴らしいものであることを伝えたある有名な詩があります。
それは、金子みすゞさんの『私と小鳥と鈴と』。
今回は、この『私と小鳥と鈴と』をご紹介します。
私と小鳥と鈴と
私が両手をひろげても、
お空はちっとも飛べないが、
飛べる小鳥は私のように、
地面(じべた)を速くは走れない。
私がからだをゆすっても、
きれいな音は出ないけど、
あの鳴る鈴は私のように、
たくさんな唄は知らないよ。
鈴と、小鳥と、それから私、
みんなちがって、みんないい。
(『金子みすゞ名詩集』彩図社 P14「私と小鳥と鈴と」より)
作者『金子みすゞ』
この詩の作者はご存知の通り童謡詩人『金子みすゞ』さんです。
実は「みすゞ」はペンネーム。本名は「テル」といいます。
「みすゞ」という名前は、信濃の国の枕詞「みすずかる」という言葉の響きが好きでつけたものなのだそうです。
明治36年(1903年)山口県長門市に生まれ、大正から昭和にかけて活躍しました。
昭和5年(1930年)26歳の若さでこの世を去りましたが、約500編の詩を残しました。
小さな動植物のいのちや人のこころ、子どもに思いを馳せ、優しい言葉で綴られたその詩の数々は、およそ100年後を生きる私たちの心にも響く奥深いものばかりです。
脚光を浴びる金子みすゞの詩
金子みすゞは当時、西条八十らに称賛されており、若い童謡詩人の憧れの存在でした。
今も注目を集める金子みすゞの作品ですが、没後半世紀は忘れ去られていたのです。
童謡詩人矢崎節夫により再発掘され、1984年に「金子みすゞ全集」が刊行されたことで再評価されました。
しかし、現在のように誰もが知る童謡詩人として注目されるようになったのは、東日本大震災がきっかけ。
東日本大震災の後、企業各社がCMの放送を自粛し、ACジャパンのCMが多く露出する事態となりました。
その時取り上げていたのが、金子みすゞの作品のひとつである『こだまでしょうか』。
このCMがきっかけで「金子みすゞ全集」の売り上げが伸び、金子みすゞへの注目が集まりました。
他の作品も注目されるようになり、『私と小鳥と鈴と』は小学校の国語の教科書でも採用されるようになりました。
今回ご紹介している『私と小鳥と鈴と』は『大漁』と並び、金子みすゞの代表作とされています。
みんなちがって、みんないい
『私と小鳥と鈴と』で、登場するのは「私」と「小鳥」と「鈴」の三者。
「私」は「小鳥」と「鈴」を見て“それぞれにできること、できないことがある“と三者三様であることを見出します。
「私」は「小鳥」のようにお空は飛べない
「私」は「鈴」のようにきれいな音は出ない
「私」は「小鳥」や「鈴」にはなれません。
それと同じように、
「小鳥」は「私」のように地面(じべた)を速くは走れない
「鈴」は「私」のようにたくさんな唄は知らない
「小鳥」や「鈴」も「私」にはなれないのです。
同じにはなれないけれど、違うからこそ世界は広がる。
それぞれできないことはあるけれど、互いのできることで支えあっている。そんな関係がそこにはある。
そう読み取ることができるのではないでしょうか。
そしてここに「鈴」が入っていることで、その支え合う関係は生物同士だけではなく、物質も含めたこの世にある全ての存在が関係していることを表しています。
そのことから全ての存在が平等で、それぞれ尊重されるものだ、というメッセージが込められていると考えられます。
さらに、タイトルは「私と小鳥と鈴と」。
「私と小鳥と鈴」ではなく「と」が最後に付けられていることで、その後にさまざまなものが続くことを表しています。
このタイトルから「みんなちがってみんないい」の「みんな」が「私と小鳥と鈴」の三者だけではなく、「この世の全ての存在」を意味していると考えることができますね。
互いの存在を認め合い、支え合い、感謝する。
その大切さを伝えたかったのではないでしょうか。
私は「多様性を受け入れる社会」の根底には、この詩が伝えているこうした考えが必要だと思います。
私たちが存在するために、たくさんのものが支えてくれていて、自分もまた何かの支えになっている。自然の一部であること。
その自然は、それぞれに違いがあることで成り立つものだということ。
だからこそ違いを認め合い、自分ができることで支え合うことが大切だということ。
こうした「目には見えないけれどある」自然の仕組み。それを感じ取る力が私たちには必要だと思います。
病気があるから、障害があるから、性的マイノリティだから、海外ルーツがあるから…などといった「違い」を人は排除したがるものです。しかし認め合うことで、工夫が生まれ、社会は発展していくのではないでしょうか。
どんな人にも他者とは違うところが必ずあります。
それはダメなことなのでしょうか?きっと違うからこそ誰かの助けになることだってあります。
「良い」という価値観を限定的なものにせず、いろんな視点で「良い」を探す。それこそが多様性を受け入れるということなのではないかと私は考えています。
最後に
金子みすゞさんの作品は、童謡という形で小さい子どもにもわかる優しい言葉が使われています。
約100年も前の詩ですが、今の私たちにも素直に理解できますよね。
ひとつひとつの詩が、心を穏やかにしてくれます。
子どもと一緒に読んで、どう感じたか親子で話し合ったり、
朗読、絵、映像、音楽 などで表現してみたり、
今よりずっと制限の多かった激動の時代で、何を見て、何を思ったのか。と作者に思いを馳せてみたり、
楽しみ方はそれぞれだと思います。
あなたの心を動かす瞬間をたくさん味わってください。
今回は多様性というテーマで『私と小鳥と鈴と』をご紹介しましたが、
これをきっかけにして、他の詩にも触れてみてもらえるといいなと思います。
子どもが読みやすいように、漢字を減らした子ども向けの詩集もあります
<参考>
最後までお読みいただきありがとうございます
▽いいね♡
▽現在のランキング順位を見る
【匿名電話カウンセリング ボイスマルシェで活動しています🌸】
・誰かに聴いてもらいたい
・どうすればいいかわからなくて苦しい
・不安で眠れない
・子育ての悩み
・身近な人の発達障害の悩み
🍀こんな時はお気軽にご相談ください🍀
▽ボイスマルシェでのご予約はこちらから
https://www.voicemarche.jp/advisers/1006
※女性専用となります。
【ココナラでメールカウンセリングをしています🌸】
・発達が気になるお子さんの子育てについて
・お子さんの困った行動への悩み
・保育園などの福祉施設の職員さんが抱える支援の悩み
🍀こんなお悩みをご相談ください🍀
▽『心理カウンセラー 松田ちかこ』ってどんな人?
▽最新情報・豆知識をチェック
▽また読みたいな
▽著書